ニュースの要点
日本医療機能評価機構は6月25日、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例2025年No.6」を公表した。
- 患者の理解の確認不足:タリージェ錠5mg [調剤]
- 本事例は、継続して処方されていた薬剤が増量になり規格が変更された際、薬剤師は規格の変更を説明したが、服用方法を正しく理解しているか患者に確認しておらず、患者が誤って2倍量を服用した事例である。
- 薬剤師は、交付時に患者に説明を行ったとしても、患者の思い込みや聞き間違い、薬袋や薬剤情報提供書の読み間違いなどにより、患者に正しい服用方法が伝わらない可能性があることを認識しておく必要がある。
- 交付時、薬剤師は一方的に説明を行うのではなく、薬袋や薬剤情報提供書の記載内容を患者と一緒に確認しながら情報を漏れなくわかりやすく伝え、患者が正しく理解しているか確認することが重要である。
- 病態禁忌:PL配合顆粒[疑義照会・処方医への情報提供]
- 本事例は、患者への聴取やお薬手帳から患者が服用している薬剤を把握できなかったため、薬剤師がオンライン資格確認等システムを活用して薬剤情報を入手し、処方医に情報提供を行ったことにより、病態禁忌に該当する薬剤の交付を未然に防いだ事例である。
- 処方監査では、患者が服用している薬剤や現病歴・既往歴、副作用歴などの情報をもとに処方内容の妥当性を確認することが求められる。そのためには、患者からの聴取やお薬手帳、マイナ保険証によるオンライン資格確認等システムなどの様々な情報源から情報を収集することが重要である。
- 薬剤師は、お薬手帳やマイナ保険証などを使用して医療機関・薬局・患者間で情報を共有することが安全な薬物療法を行うために重要であることを患者に説明し、それらの活用を促すことが望ましい。
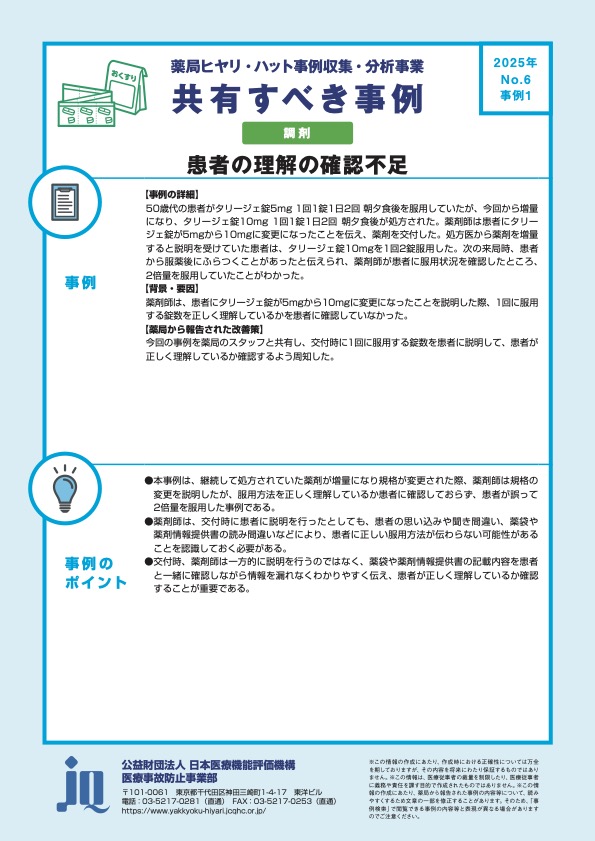
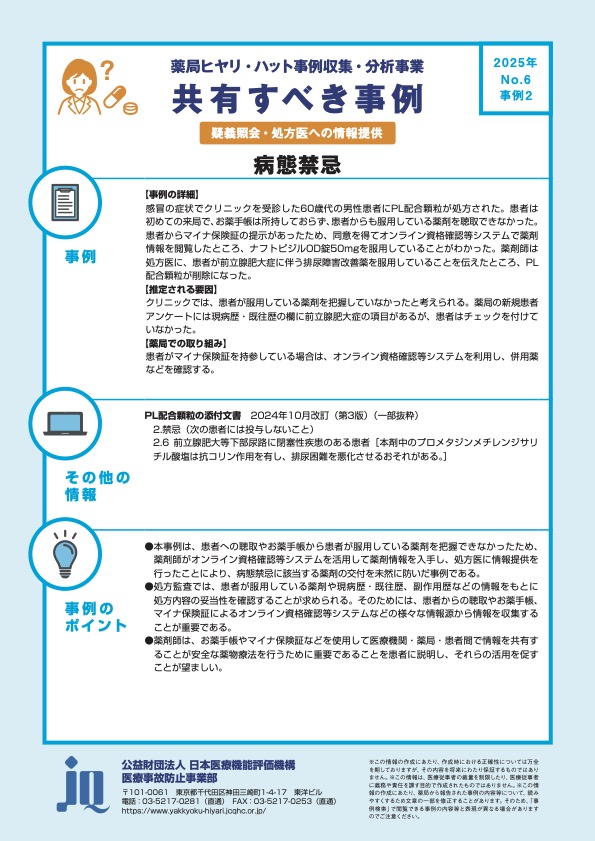
(https://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/sharing_case_2025_06.pdf)



