ニュースの要点
日本医療機能評価機構は10月27日、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例2025年No.10」を公表した。
- 用法:フォゼベル錠5mg[疑義照会・処方医への情報提供]
- フォゼベル錠は2024年2月に販売開始された高リン血症治療薬である。高リン血症治療薬は、腸管からのリンの吸収を阻害することにより血清リン濃度を低下させる薬剤であり、一般的に用法は食直前もしくは食直後に設定されている。フォゼベル錠は食直前に服用することで最も高い効果を得られる薬剤であるため、処方監査を行う際は用法が食直前であるか確認を行う必要がある。
- 新医薬品を薬局で採用した際は添付文書やインタビューフォームなどを確認し、効能・効果、用法・用量、重要な基本的注意、禁忌、相互作用、副作用などの基本情報を把握しておく必要がある。さらに、薬局内のすべての薬剤師が知識を持てるよう、これらの情報は薬局内で共有することが重要である。
- 本事業の第33回報告書(2025年9月公表)では「新規収載医薬品※に関する事例」を取り上げ、フォゼベル錠に関する事例を分析した。疑義照会や処方医への情報提供に関する事例では、用法間違いの事例のほか、服薬後の患者の症状から副作用発現の可能性を疑い処方医へ情報提供した事例などを紹介している。
- 病態禁忌:オランザピン錠[疑義照会・処方医への情報提供]
- オランザピン錠は、服用により高血糖があらわれ、糖尿病性ケトアシドーシス、糖尿病性昏睡から死亡に至るなどの致命的な経過をたどることがあるため、糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者には禁忌である。
- 本事例は、患者にオランザピン錠が処方された際、薬局で管理していた情報から患者が別の医療機関で糖尿病の治療を行っていることに気付いた薬剤師が疑義照会を行い、オランザピン錠の服用を防いだ事例である。
- 薬剤師は、複数の医療機関を受診している患者が安全に薬物治療を受けられるように、患者の現病歴や既往歴、薬剤服用歴などを一元的・継続的に管理し、処方された薬剤が患者に適切であるか検討することが重要である。
- 適切な薬物治療を行うには、患者の現病歴や併用薬の情報が不可欠である。薬剤師は、それらの情報を医療従事者と共有するにはお薬手帳の提示などが有用であることを、日頃より患者に伝える必要がある。
- 処方漏れ:一硝酸イソソルビド錠20mg[疑義照会・処方医への情報提供]
- 本事例は、入院中に追加された薬剤が退院後に処方されていないことに気付いた薬剤師が疑義照会を行った結果、薬剤が追加になり治療が継続された事例である。
- 退院後は、紹介状の記載漏れや医療機関間の情報伝達不足、退院サマリーの読み間違いなどにより、薬物治療が正しく引き継がれないことがある。
- 患者から入院していたことを聴取した際は、お薬手帳や薬剤管理サマリー、患者から聴取した情報をもとに、入院前、退院時、退院後に処方された薬剤を比較し、変更点がある場合はその経緯
- 背景を把握したうえで、薬物治療が正しく引き継がれているか確認を行う必要がある。・退院後の処方漏れや間違いを見逃さないために、退院後の初回処方時に確認する内容を手順書に定めて、遵守することが重要である。
- 本事業部が運営している医療事故情報収集等事業は、第77回報告書の分析テーマで「退院前後の処方間違いに関連した事例」を取り上げた。入退院に伴い抗凝固薬の処方漏れが起きた際、保険薬局は処方されていないことに気付いていたが疑義照会を行わず、その後、患者が脳梗塞を発症した事例を掲載している。薬剤師は、患者の薬物治療が適切に継続されなかった場合、患者に大きな影響を及ぼす可能性があることを認識し、退院後は特に注意して処方監査を行うことが重要である
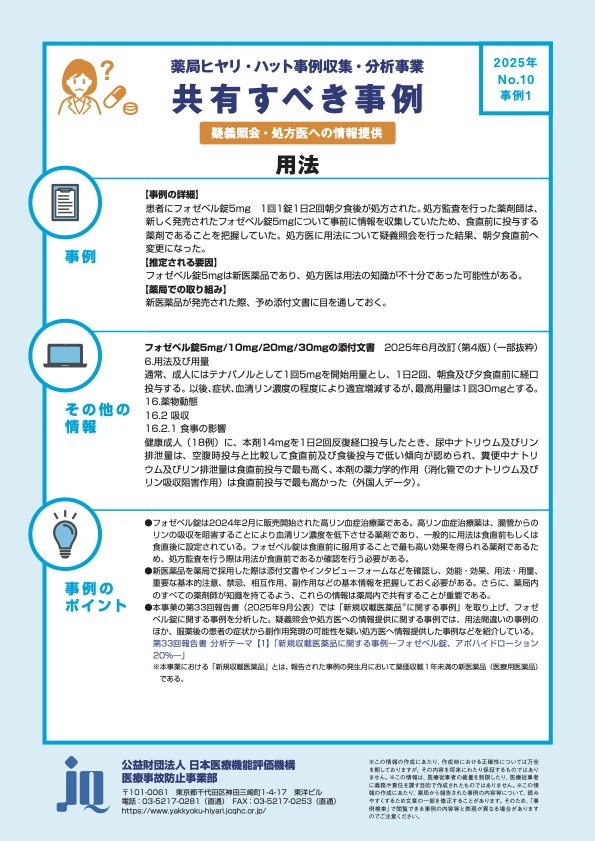
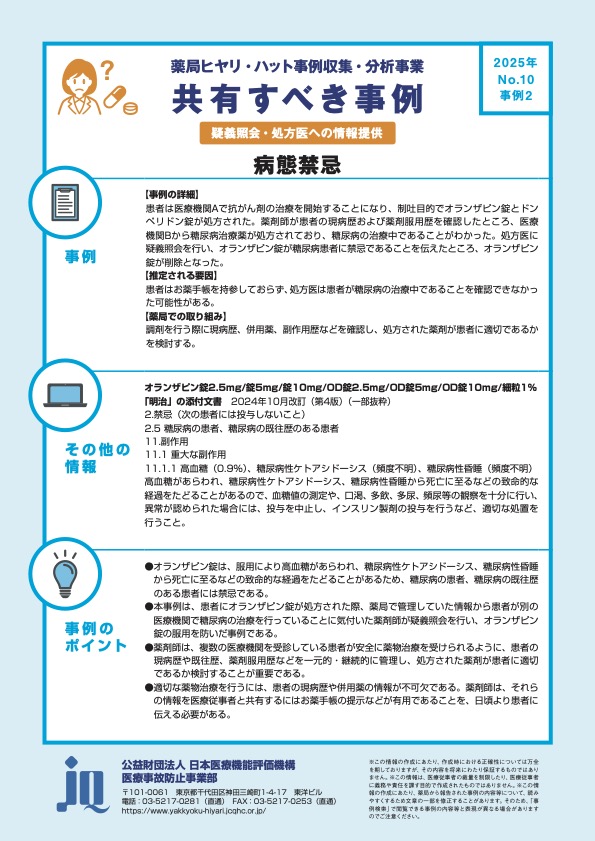
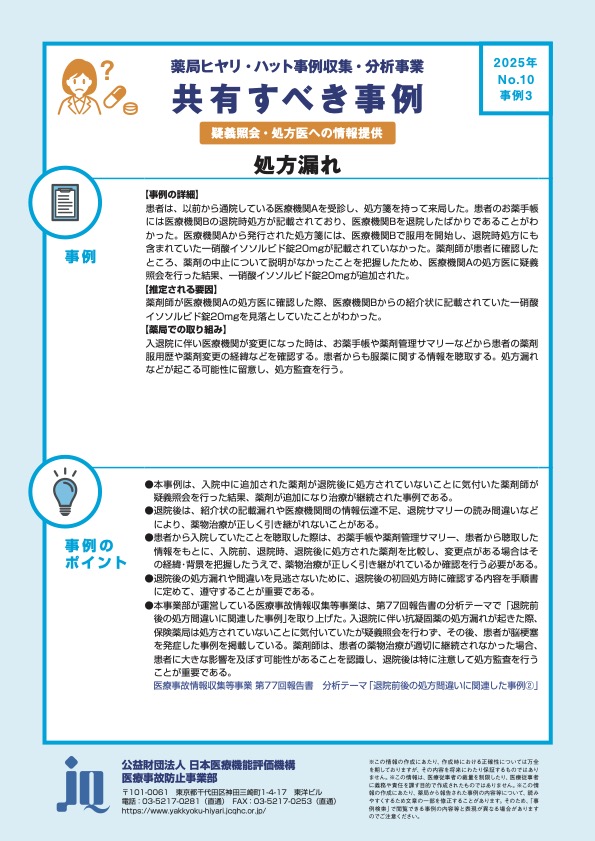
(https://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/sharing_case_2025_10.pdf)



