ニュースの要点
日本医療機能評価機構は9月25日、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業の「共有すべき事例2025年No.9」を公表した。
- 処方箋の確認漏れ:ロナセンテープ20mg[調剤]
- 本事例は、医療機関から処方箋が2枚発行された際、2枚目のみを応需した薬局が処方箋の通し番号を確認せず、1枚目の処方箋の存在に気付かないまま調剤を行った事例である。
- 処方箋を応需した際は、処方箋の通し番号や「次頁あり」「前頁あり」「以下余白」などの文言を確認し、発行された処方箋が全て揃っているか確認することが重要である。繁忙時や閉店業務中という通常とは異なる状況下においても遂行できるよう、確認項目をリスト化し薬局内に掲示するなどの対策を行うことが望ましい。
- 本事業に報告された、患者が処方箋の一部を提出し忘れた事例には、薬剤師が患者から症状や服薬状況を聴取したことにより処方箋の提出漏れに気付いた事例もある。
- 薬剤師は、薬剤服用歴やお薬手帳、患者から収集した情報をもとに処方監査を行い、患者による処方箋の提出漏れや医療機関での処方箋の交付漏れがないかを確認することが重要である。
- 自己注射の手技の確認不足:ランタスXR注ソロスター[調剤]
- 患者は、自己注射を長期間使用しているうちに注射時の注意事項を忘れたり、手技を自己流に簡略化したりする可能性がある。薬剤師は、患者が薬剤の注射方法や管理方法を理解し正しく使用できているかを定期的に確認し、薬剤服用歴に記録を残して薬剤師間で共有する必要がある。
- 本事業に報告された自己注射薬に関する事例には、血液の混入の他に、注入時に薬液が出ない、注入ボタンを押すと重く感じるなどの患者からの申し出に薬剤師が対処した事例がある。
- 自己注射薬に不具合や異常が生じた場合は、患者が誤った方法で薬剤を使用・管理している可能性がある。使用時に何か異常を感じた場合は速やかに医師や薬剤師に相談するよう、患者にあらかじめ伝えておく必要がある。薬剤師は、適切な薬物治療が安全に継続できるように支援することが重要である。
- 病態禁忌:ドンペリドン錠10mg「JG」[疑義照会・処方医への情報提供]
- プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍(プロラクチノーマ)は、乳汁分泌作用のあるホルモンであるプロラクチンが過剰に産生される下垂体腫瘍である。本事業には、プロラクチン分泌性の下垂体腫瘍(プロラクチノーマ)の患者に禁忌であるドンペリドンやスルピリドが処方されたため、処方医に疑義照会を行った事例が2020年4月1日~2025年6月30日に16件報告されている。報告された薬剤は、ドンペリドンが13件、スルピリドが3件であった。
- 患者は、自身の現病歴を正確に記憶していない場合や、把握していても、医療機関で医師に伝えない場合がある。薬剤師は、患者に情報共有の重要性を伝え、お薬手帳に現病歴・既往歴・副作用歴などを記載して、医療機関や薬局で毎回提示するよう説明する必要がある。
- 安全で有効な薬物治療を行うため、薬剤師は現病歴・既往歴や併用薬、副作用歴などの情報を患者から収集し、それらの情報を考慮したうえで処方内容の妥当性や服用中の薬剤による副作用発現の可能性を検討することが重要である。
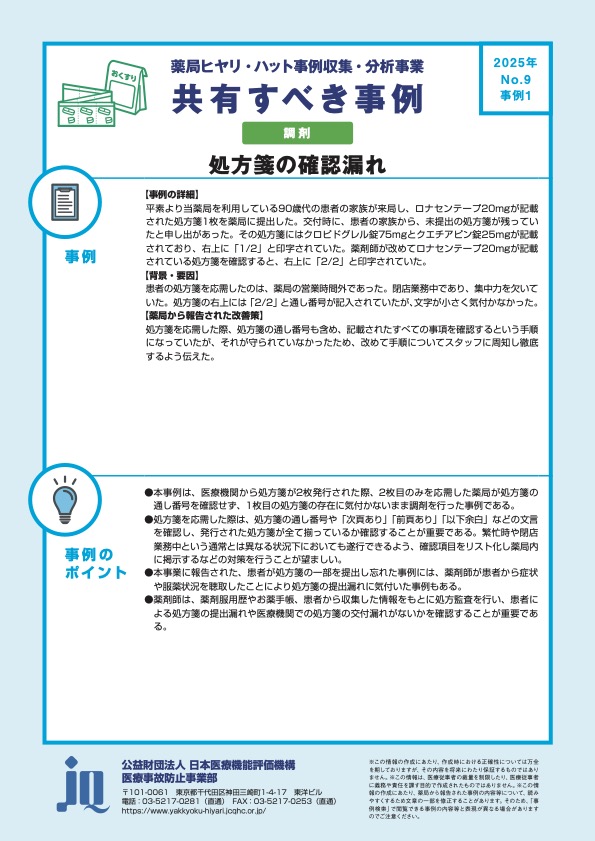
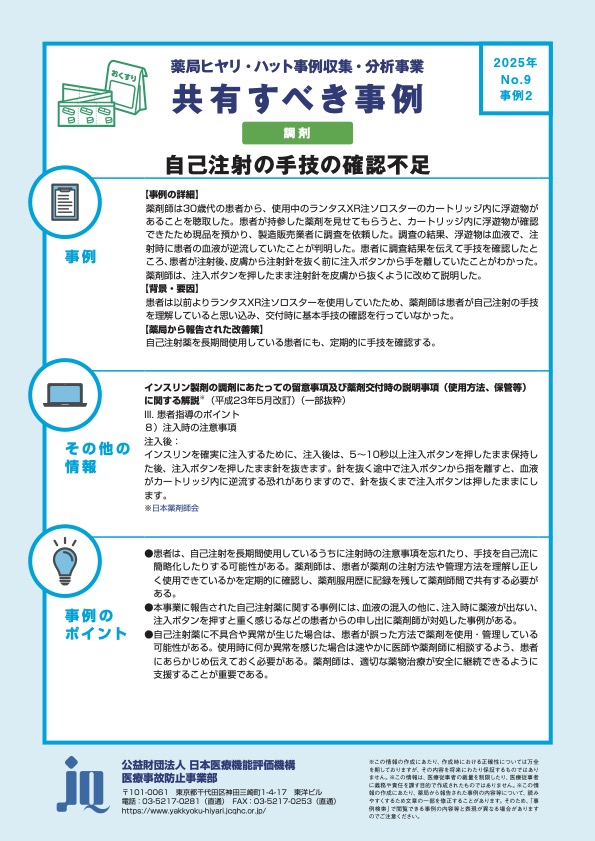
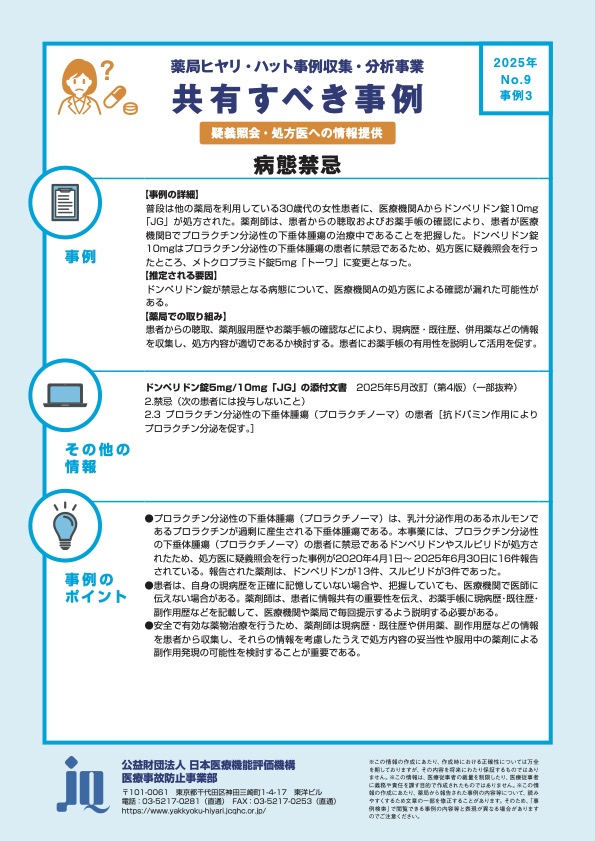
(https://www.yakkyoku-hiyari.jcqhc.or.jp/pdf/sharing_case_2025_09.pdf)



